出張は多くのビジネスパーソンにとって日常的な業務の一部ですが、その費用の取り扱いについて、正確に把握できている方は意外と少ないのではないでしょうか。
本記事では、2023年に財務省が実施した「民間企業における出張旅費規程等に関するアンケート報告書」をもとに、出張費用の支給実態や旅費精算の課題について、従業員目線で解説します。とくに「日当」「宿泊費」「食事代」といった項目の取り扱いに関心のある方は必見です。
下記財務省のサイトより引用しています。概要を本ブログで紹介しますが、もっと知りたい方はこちらをご確認ください。
出張費用とは?|基本構成をおさらい

出張費用には主に以下の項目が含まれます。
- 交通費:電車・バス・飛行機などの移動費
- 宿泊費:ビジネスホテルや宿泊施設の料金
- 日当:時間的拘束・雑費への補填
- 食事代:朝・昼・夕の各食に対する手当(企業によっては日当に含まれる)
- 荷造運送費:長期赴任に伴う引越し費用(主に赴任時)
企業の旅費規程によって、これらの支給方法や金額設定は大きく異なります。そのため、従業員としても自社の制度内容を正確に理解しておくことが重要です。
日当の支給実態|支給される企業は約9割

支給の有無と判断基準
財務省の調査によると、国内出張において日当を支給している企業は88.4%にのぼります。「日当は支給しない」と回答した企業は11.6%にとどまり、全体として日当制度は依然として広く浸透しています。
支給の判断基準としては、以下のような傾向があります。
- 行程距離によって判断:49.4%
- 宿泊の有無によって判断:44.8%
- 出張時間・地域等による判断:20%未満
企業ごとの運用ルールを確認しなければ、「条件を満たしているのに申請していなかった」という事態にもなりかねません。
支給額の水準
- 平均日当:2,621円
- 最低額の平均:1,780円
- 最高額の平均:3,786円
出張日当の金額は、役職や条件に応じて複数区分を設けている企業も多く、おおよそ1,000~4,000円の範囲に収まるケースが大半です。
宿泊費の取り扱い|上限付き実費支給が主流

宿泊費については、次のような支給方式が確認されています。
- 上限付き実費支給:43.7%
- 定額支給:28.9%
- 実費支給(上限なし):24.0%
最も一般的なのは「上限付き実費支給」です。これは、領収書等による実費を精算しつつも、企業側が一定の上限額を設定する方式です。私の勤務する会社もこの上限付き実費支給となっています。一般社員の場合、都市部は11,000円、地方は9,000円の上限が決められています。
支給額の平均
- 定額+上限付き実費支給企業の平均額:10,672円
- 上限付き実費支給企業の平均額:11,304円
都市部や繁忙期の宿泊料金が上限額を超える場合、差額を自己負担するケースもあるため注意が必要です。私の勤務する会社では昨今の宿泊費高騰を受けて事前の承認を得ることで実質上限を超えての宿泊も可能となっています。
食事代の支給は少数派 貰えてればラッキーかも・・・

一方で、食事代を別途支給している企業は非常に少数です。
- 朝食代の支給なし:89.1%
- 昼食代の支給なし:92.6%
- 夕食代の支給なし:90.0%
支給している企業における平均額は以下のとおりです。
| 食事区分 | 平均支給額 |
|---|---|
| 朝食 | 971円 |
| 昼食 | 1,007円 |
| 夕食 | 1,305円 |
企業によっては、これらの食費を「日当」に包括している場合もあります。
旅費精算の実務|見落としがちな注意点

出張費用は、事前の申請と事後の精算手続きが正確に行われて初めて支給されます。従業員側の「うっかり」によって、実費を取り損ねることもあります。
以下のようなケースには注意が必要です。
- 宿泊費の上限を超えたが自己申告しなかった
- タクシー代が認められない条件だった
- 精算書の提出期限を過ぎてしまった
自社の旅費規程や経理部門の運用ルールを事前に確認することが、損をしない第一歩です。
課税対象の確認も重要
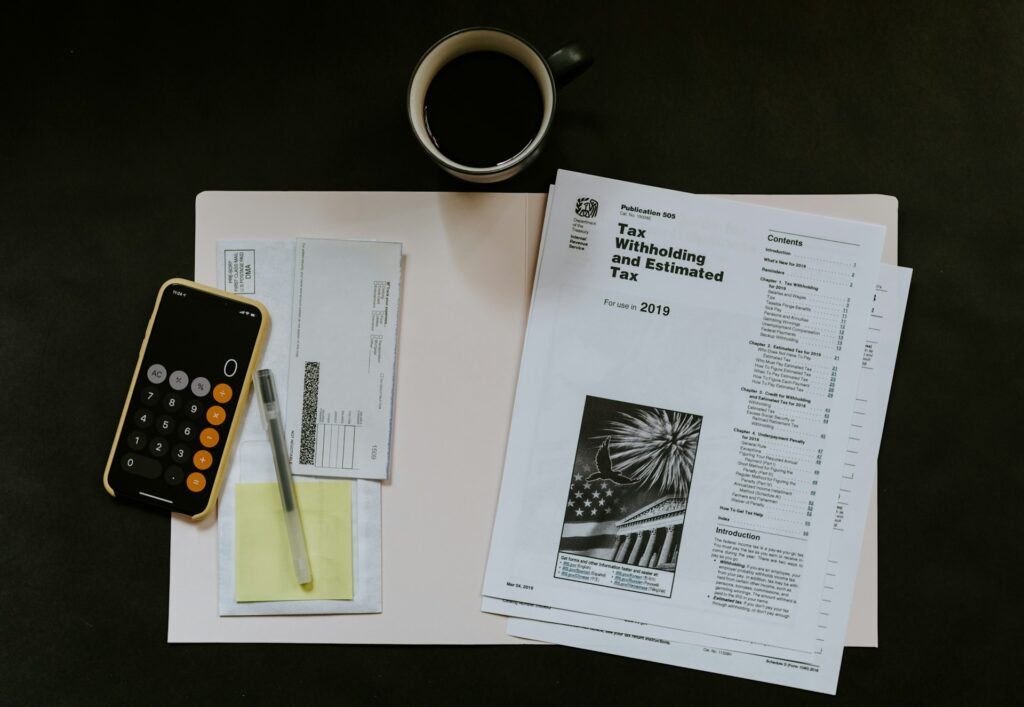
支給される出張費用が「給与」と見なされるか否かは、税務処理上の重要なポイントです。一般に、実費精算分や一定の非課税日当は課税対象外とされていますが、一定額を超える手当や支給方法によっては所得税の課税対象となる場合もあります。
給与明細や源泉徴収票で、「課税対象」として反映されていないかを確認しておくことを推奨します。
従業員が確認しておきたいポイント一覧
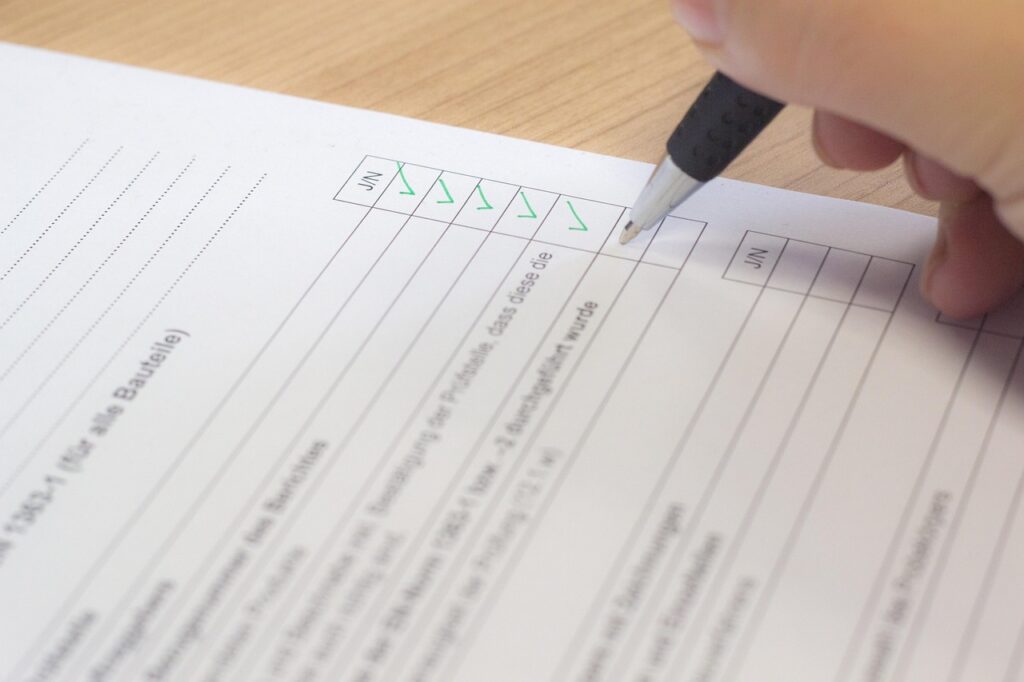
出張に際して、以下の点を事前に確認しておくと安心です。
- 自社の旅費規程(特に日当・宿泊費・食事代の取り扱い)
- 各費用の支給条件(距離・日数・時間など)
- 宿泊費の上限額と支給方式
- 領収書の提出ルールと精算の期限
- 日当の課税/非課税の判断基準
まとめ|出張費用の知識は“自己防衛”にもつながる

出張費用は、単なる経費処理の問題ではありません。従業員が正しく制度を理解し、適切に申請・精算することによって、公平な処遇が保証される重要な要素です。
特に出張の多い方にとっては、旅費の取り扱いがモチベーションや業務負担に大きな影響を与えることもあります。
日当が支給されるのか、宿泊費の上限はいくらか、精算はいつまでに行う必要があるのか。
これらを把握し、自らの労務に見合った費用を正当に受け取る意識を持つことが、健全な労使関係にもつながります。



コメント